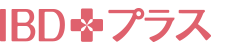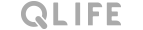炎症性腸疾患の新薬開発における重要課題を解決する、新しい抗体の作製技術を確立
ニュース | 2025/8/22
ヒトとマウス、種の違いが新薬開発の障壁になることがある
東京薬科大学は、鳥取大学、鹿児島大学との共同研究で、炎症性腸疾患(IBD)や大腸がんの治療の可能性を大きく広げる新しい抗体の作製に成功したと発表しました。
新薬の開発では臨床試験の前に動物実験が行われますが、マウスやラットで良好な結果が得られても、ヒトでは同じような効果が確認できないことは少なくありません。これは「種の壁」と呼ばれ、医薬品開発の大きな課題の一つです。
Glycoprotein A33(GPA33)は、腸の表面にある細胞の目印のような役割を果たすタンパク質で、IBDや大腸がんなどの腸の病気の治療において、非常に有望な標的として長年研究されてきました。しかし、「種の壁」が原因でヒトとマウスに共通して作用する抗体を作ることが難しく、30年以上にわたって有効な治療薬の開発には至っていませんでした。
「種の壁」を克服する抗体作製法を確立、さまざまな疾患への応用にも期待
研究グループは、独自の技術を用いて、体内でヒトと同じタイプの抗体を作ることができる特殊な動物を開発していました。今回、この動物を使って、ヒト・マウス・ラットの全てに共通して作用する世界初の抗GPA33抗体の作製に成功しました。
実際に新しい抗体をマウスに投与したところ、標的である腸の組織に選択的に集まることが確認されました。これにより、抗体を利用すれば薬を必要な臓器にピンポイントで届け、治療効果を高めながら副作用を抑制できる可能性が示されました。また、この抗体はヒトにも作用するため、動物実験で良い結果が得られれば、ヒトでも同様の効果が期待できると考えられます。
今回の研究で作製した抗体は、これまで困難だった動物実験での評価を可能にし、GPA33を標的とする診断・治療法の開発を大きく前進させるものです。さらに、この抗体作製法は、他の創薬ターゲットにも応用できるため、「種の壁」に阻まれてきた疾患の治療薬開発への貢献が期待されます。
(IBDプラス編集部)