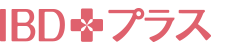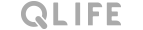【JSIBD市民公開講座】小児IBDの病態と治療、求められる支援について(埼玉県立小児医療センター 消化器・肝臓科 南部隆亮先生)
ニュース | 2024/2/29
成人に比べ患者数が少なく、専門で診ている施設も少ないことから本人やご家族が戸惑う場面も多い小児IBD。病気の経過と必要になる検査・治療は?成人での治療と異なる点は?そんな多くの疑問に対して、埼玉県立小児医療センター 消化器・肝臓科 南部隆亮先生が、わかりやすく解説してくださいました。
小児IBDの特徴は?VEO-IBD、IBDU、Monogenic IBDって何?
小児IBD患者は世界中で増加しており、成人発症例に比べて遺伝的要因が強いということがわかってきています。南部先生によると小児潰瘍性大腸炎は、全大腸炎型が約75%(成人は約40%)、ステロイド依存・抵抗例などの難治例が約45%(成人は約20%)、手術に至るのは2年で11%(成人は5年で12~14%)と、重症・難治例が多いそうです。小児クローン病は、約60%が小腸と大腸の両方に病変があり病変範囲が広いという特徴があります。また、34%に肛門病変があるそうです。さらにステロイドの副作用や栄養障害による成長障害が大きなネックとなるため、早期から生物学的製剤を使うこともあると述べました。加えて、小児クローン病の合併症の1つとして、「口唇肉芽腫症(Orofacial granulomatosis:OFG)」を指摘。これは、唇・口角・歯肉が腫れて痛みなどが出る病気で、OFGの症状がクローン病の症状に先行して見つかる場合もあるそうです。治療にはステロイドが使われますが、有効率が50%程度(腸管病変は約80%)で治療が困難になることもある一方で、唇が腫れる以外は痛みを感じる患者さんは少ないと説明しました。
次に、6歳未満で発症する「超早期発症型炎症性腸疾患(very early onset infl ammatory bowel disease : VEO-IBD)」と、潰瘍性大腸炎かクローン病かが区別できない「分類不能型腸疾患(IBDU)」について解説しました。VEO-IBDはほとんどが大腸単独型で、腹痛が少なく粘血便が多いという傾向があるそうです。腹痛が少ないのは患者さんにとっては良いことですが、周囲が気付きにくく、知らない間に重症化しやすいという点には注意して欲しいと述べました。また、VEO-IBD はIBDUの割合が多く、さらに約10%は「Monogenic IBD」である可能性が高いそうです。
Monogenic IBDとは「たった一つの遺伝子の異常で発症するIBD」のことで、典型的な潰瘍性大腸炎やクローン病とは大きく異なります。2歳未満発症の約10~15%、6歳未満発症の約7~10%に隠れているとされます。この遺伝子の異常というのは両親、きょうだい、親戚から引き継いでいることがあるため、家族歴(近親者の既往歴)にIBD・免疫不全症・非典型的な感染症になった人がいる場合が多いそうです。Monogenic IBDには80個程度の遺伝子が関連しているそうですが、日本では保険診療で日本人に多いとされる17個の遺伝子検査が可能とのこと。Monogenic IBDは皮膚症状、自己免疫疾患(貧血、甲状腺異常など)がある場合や、手術・骨髄移植などを要する難治例も多いため、医師が見て特徴に当てはまる場合は、早期に遺伝子検査が行われるそうです。
1~2年に1回は大腸内視鏡検査を。各治療法のメリット・デメリット
南部先生曰く、他の子たちと変わらない生活を送らせてあげるためにも、成長障害の評価のためにも、血液検査や便検査でこまめに炎症や栄養状態を見ていくことが大切。また、将来的な大腸がんリスク低下のためにも粘膜治癒を目指すべきだとしました。そのためには便中カルプロテクチン検査を行いながら1~2年に1回の大腸内視鏡検査が理想的。小学生以下の患者さんはIBDUである可能性もあるため、上部消化管内視鏡検査も必須だと考える、と語りました。
クローン病では多くの場合、ステロイドや生物学的製剤を使用する前に安全性の高い「部分経腸栄養療法」や「完全経腸栄養療法」が行われますが、味の問題などで継続できない患者さんも多いことが知られています。しかし、完全経腸栄養療法は6~8週間の継続でステロイドと同等の効果がある(日本では2~6週間で行われることが多い)という欧米の報告があるとのこと。さらに、部分経腸栄養療法も1日に900ml程度の摂取で免疫調節薬と同等の効果があるので、可能な範囲で継続して欲しいと語りました。
ステロイドに関しては、使い過ぎると成長障害などの副作用が出るため、3か月位で中止することが理想的だとしました。また、生物学的製剤に関しては「小児で使用できるのはインフリキシマブとアダリムマブのみとされているが、それ以外が使えないということではなく、この2剤がどうしても効かない場合は他の生物学的製剤が使用されることも多い」と述べました。
日本の300症例のデータで見る手術率、生物学的製剤使用・継続率
南部先生が示した日本の300症例のデータによれば、小児潰瘍性大腸炎の手術率は、発症時に重症の場合は2年以内に25%、軽症~中等症は7.5%が大腸切除に至っていました。また、生物学的製剤の使用率は、重症の場合は2年以内に65%、軽症~中等症は25%が使用していました。インフリキシマブの継続使用率は、2年間で約半数が継続中止となっており、中止後1年で約50%弱、2年で約50%が大腸切除に至っていました。しかし、さまざまな薬剤が登場した2018年の6月以降では、大腸切除に至る率が有意に下がっていることがわかりました。
小児クローン病においては、予後不良予測因子を有する場合は時期を逸さずに生物学的製剤を使用することが推奨されています。予後不良予測因子とは「成長障害、大腸・小腸の広範の病変、大腸の深い病変、肛門病変、狭窄・穿通」のことです。埼玉県立小児医療センターでは、インフリキシマブ・アダリムマブともに2年で60%程度の継続使用率で、その後、ウステキヌマブに切り替える例が多いそうですが、ウステキヌマブは2~3年で80%継続使用できているそうです。南部先生はこの結果を受けて「やはり新規薬剤も使用していくことで、良い状態が維持できると考えられる」と、述べました。
一方、近年はパラドキシカルリアクションで生物学的製剤を中止するケースも多いそうです。これは生物学的製剤の長期使用で出てくる乾癬様の皮疹のこと。生物学的製剤が効いていても、この皮疹のために中止せざるを得ない患者さんもいるそうです。このような皮疹は足の裏や、靴下で隠れている部分のみに出て見えない場合もあるので注意が必要とのことでした。
クローン病患者の一人として、子どもたちの背中を押してあげられるように
最後に南部先生は、自身もクローン病患者であることを明かし、自らの体験と想いを語り、講演を締めくくりました。
発病した23歳当時は、自分がクローン病患者だという実感はあまりなかった。しかし、結婚して子どもを授かるというフェーズになってからは、責任が出てきたせいか、自分が患者だという意識が自然と高まってきた。病気の受容については医療者の自分でも、とても時間がかかった。IBDは思春期の発症も多く、15%程度の小児IBD患者さんたちが不安症状や抑うつ症状を抱えているという報告もある。これが全ての子どもたちに当てはまるわけではないが、自己肯定感を保って欲しいし、病気があってもなりたい自分になって欲しい。そのためにも、周囲に助けを求めて欲しい。親御さんたちは、子どもがチャレンジしたいと言った時に背中を押してあげて欲しい。私も子どもたちの背中を押してあげられるような医療者になりたいと思っている。
(IBDプラス編集部)