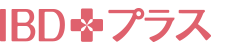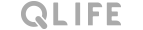クローン病の検査|血液・尿・便検査、内視鏡など、各検査について解説
クローン病 | 2023/6/29 更新
どんな検査をするの?(クローン病)
血液・尿・便検査でわかること
血液検査では、炎症の度合いや、炎症による出血が原因となって起こる貧血の有無、栄養状態など、幅広い病状を検査します。炎症の度合いは、白血球数、血小板数、赤血球沈降速度、CRP(血清C反応性タンパク)の値でわかります。炎症が起きていると、白血球の数と血小板の数がそれぞれ増加、赤血球沈降速度が上昇し、CRPが増加します。
クローン病では、栄養を吸収する小腸でも炎症が起きていることが多く、小腸に炎症が起こると栄養状態が悪化します。この場合には、血中の総たんぱく値、たんぱく質の1種であるアルブミン値、総コレステロール値が低下傾向を示します。
クローン病による炎症では、病変などからの出血するため、鉄欠乏性貧血になりやすいことが知られています。貧血になると、赤血球の数、赤血球のなかに含まれているたんぱく質(ヘモグロビン)の値、血液中に占める赤血球の割合(ヘマトクリット)などが正常値よりも低くなります。
尿検査では、主に症状の悪化による脱水症状がないかを尿の比重で判定するほか、尿路感染症や尿路結石などの合併症や、薬剤による副作用の有無を調べます。
便検査では、同時にほかの病気を合併していないかや、クローン病に似たほかの病気と鑑別するために、細菌の有無などを調べる「便培養検査」を行います。また、症状が軽い場合は、炎症した部分からの出血量が少なく、便を見ただけでは出血があるかどうかはわからないことがあります。このため、便の中に潜んでいる血液の有無を調べる「便潜血反応検査」を行います。
X線(レントゲン)検査でわかること
X線検査は、小腸、大腸にある病変の位置や広がりなど、全体像を確認するために行う検査です。画像にコントラストを付けて見やすくするため、小腸検査では口からバリウムを飲むか、鼻から十二指腸までチューブを入れてバリウムと空気を注入します。大腸では、肛門からチューブを入れ、バリウムと空気を注入してX線(レントゲン)装置で撮影します。
この検査によって、腸管内部にできるクローン病特有の4~5センチ以上の縦長の潰瘍(縦走潰瘍)、潰瘍や潰瘍周辺の腸の粘膜の丸い盛り上がりによって丸石を敷き詰めたような敷石像、瘻孔などの発生状況を観察します。
小腸の検査では現在、バルーン内視鏡がありますが、クローン病の小腸病変では、炎症が繰り返し起こることで腸管内が狭くなる狭窄や、小腸と他臓器がくっついてしまう癒着も起きやすく、バルーン内視鏡を通しにくい場合が少なくありません。また、クローン病では潰瘍が粘膜より深い位置まで達し、腸管に穴(穿孔)が開くことがあり、腸管にできた穴から腸同士あるいはその他の組織とくっついてしまう(瘻孔)ことがあります。一般に、穿孔や瘻孔の位置を内視鏡で確認することは難しいといわれており、X線検査のほうが、病変の位置や範囲を確認しやすいのが特徴です。
大腸の検査は、大腸内視鏡による検査が進歩し、最近ではX線検査が行われることは少なくなりましたが、炎症が重度で大腸内視鏡を挿入しにくい場合や、大腸内視鏡を挿入する痛みに耐えられない場合などは、この検査を行います。
大腸内視鏡でわかること
大腸内視鏡検査は、大腸にある病変の重症度や位置などを確認するために行う検査です。肛門から挿入する大腸内視鏡を使うため、大腸内部の状況を、より鮮明かつカラフルに観察できます。このため、クローン病と一部症状が似ている潰瘍性大腸炎や大腸がんとの違いも、視覚的に確認できるほか、治療の効果を確認しやすいのが特徴です。
検査前には、大腸内の便を排出させる準備が必要になります。検査前日や当日朝などに、経口腸管洗浄液と呼ばれる下剤を服用し、大腸内の便を排出します。排出物が透明になれば検査準備は完了です。この後、肛門から大腸内視鏡を挿入し、内視鏡の先から空気を送りだしたり吸い込んだりすることで、大腸を膨らませたり、縮ませたりしながら、内視鏡を大腸の先端まで送り込みます。そのうえで、大腸内視鏡を引き戻しながら、内部の様子を観察します。
バルーン内視鏡でわかること
小腸は大腸より腸管内部が狭いうえ、クローン病では狭窄が起きやすいため、内視鏡にバルーンと呼ばれる風船のようなものが合体したバルーン内視鏡で検査をすることがあります。検査では、このバルーンを膨らませて小腸の腸管を膨らましながら内視鏡を挿入していきます。バルーン内視鏡は、肛門から入れる場合と口から入れる場合とがあり、肛門から入れる場合は、大腸内視鏡検査の時のように、事前に下剤を服用して腸管内をきれいにしておく必要があります。
カプセル内視鏡でわかること
カプセル内視鏡は、小型カメラとLEDライトを内蔵した11×24mmのカプセルを、適量の水とともに口から飲み込んで行います。小腸に入ったカプセル内視鏡は、小腸の内部をデジタル動画で撮影して送信。体の外に装着したレコーダーで受信します。検査には約8時間かかりますが、病院に滞在する必要はなく、通常の生活を送りながら行うことができます。カプセル内視鏡は、その後大腸を経由して肛門から排泄されます。
カプセル内視鏡での問題は、腸管内の狭窄がひどい場合には、飲み込んだカプセルが腸内にとどまったままになってしまう危険性があることです。そのため現在では、事前に腸管を確実に通過できるかを、試験用のカプセル(パテンシーカプセル)を飲んで確認します。パテンシーカプセルを飲みこんでから、原形をとどめたまま30時間以内に排出されれば、カプセル内視鏡が使えると判断されます。
この時間内に排出されない場合もありますが、その際にはX線検査でパテンシーカプセルが原形のまま大腸まで到達しているとわかれば、カプセル内視鏡を使用しても問題ないと判定されます。
超音波検査でわかること
クローン病は、再燃と寛解を繰り返す病気です。治療を行ううえで、炎症の程度や腸の状態を確認することは重要ですが、少なからず苦痛を伴う大腸内視鏡検査や、被ばくの心配があるX線検査、CT検査を繰り返し行うことは望ましくありません。その点、超音波検査は苦痛が少なく、繰り返し行える検査であり、腸管の断層の様子も確認できます。
腸管周辺で腹水がたまっている場合や、リンパ節が腫れている場合、炎症により膿がたまっている膿瘍の位置なども、この検査で確認ができます。
CT・MRIでわかること
クローン病では、症状がひどい場合は腸管に穴が開き(穿孔)、腸管の内容物が腹腔内に漏れ出すこともあります。このような状況では、X線検査や内視鏡検査は不向きですから、CT(コンピューター断層撮影)やMRI(核磁気共鳴画像法)による検査を行います。CTとMRIの一番大きな違いは、CTでは放射線被ばくがあり、MRIではそれがないことです。CTではとても短い時間で検査ができますが、放射線被ばくの観点からは、頻繁に行うのはあまり適切ではありません。
クローン病では腸管の最下層にいたる炎症を繰り返し起こすため、腸管の壁の厚さが異常に厚くなる肥厚がかなり進行し、腸管の下の層まで炎症が達して腸管の層構造が崩れていることが多いのですが、CT、MRIいずれの検査でも、この様子を確認しやすいという特徴があります。炎症部位の血流状況や炎症が腸管周囲に位置する腸間膜に波及している様子なども観察が可能です。また、MRIではクローン病特有の縦走潰瘍や、頻繁に起こる狭窄による腸の変形状態なども、画像上で判別できます。
病理診断でわかること
病理診断は、内視鏡検査の際に実際の病変の一部を切り取って、電子顕微鏡などで病変の組織の詳細を確認する検査です。電子顕微鏡で見えたクローン病と思われる病変の組織が、細菌やウイルスによる感染性腸炎や、一部の薬剤が原因となっている腸炎、その他のクローン病と似ている病気にかかった場合の病変の組織と、様相が違うかどうかを判別します。
クローン病と疑われる場合は、潰瘍性大腸炎と違うかどうかも、同じように組織の様子から判別します。ただし、潰瘍性大腸炎とクローン病の区別は病理診断のみで判断することは難しく、ほかの検査結果も総合して判断します。
- 参考文献
-
日比紀文、久松理一編集:IBDを日常診療で診る,羊土社,2017
日比紀文監修、横山薫ほか編集:チーム医療につなげる!IBD診療ビジュアルテキスト,羊土社,2017