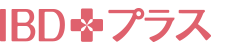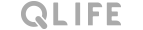【JSIBD市民公開講座】IBDに対する外科治療(東北労災病院 炎症性腸疾患センター 高橋賢一先生)
ニュース | 2022/2/1
IBD治療の大きな分岐点や転換点となり得る外科治療。メリットとデメリットを天秤にかけて、長年悩んでいる患者さんも少なくありません。講演では東北労災病院 炎症性腸疾患センターの高橋賢一先生が、外科治療に対する悩みを解消すべく、わかりやすく解説してくださいました。
潰瘍性大腸炎で手術適応となるケースは?手術の意外なメリットも
高橋先生はまず、潰瘍性大腸炎緊急手術の絶対的適応として、「大腸穿孔」「大量出血」「中毒性巨大結腸症」「強力な内科的治療が無効な重症・劇症例」を挙げました。かつては、強力な治療はステロイドしかありませんでしたが、現在は、シクロスポリン、インフリキシマブ、タクロリムスなど、たくさんの選択肢があり、重症例の治療成績は向上しています。一方で、これらの治療が無効な患者さんも必ずいらっしゃいますし、どの治療が有効でどの治療が無効であるかは患者さんによってさまざまです。
患者さんごとに、どの治療が効果を示すのか予測ができれば、手術を含めたより的確な治療選択を行うことが可能になります。高橋先生は、「現在、個々の患者さんの治療効果を明らかにするため、厚生労働省の研究班において、大規模な症例登録研究(レジストリ研究)が開始された」と、述べました。
次に高橋先生は、待機手術の絶対的適応として、「大腸がん」「高度異形上皮」を挙げました。潰瘍性大腸炎に伴う大腸がんは、症状が出にくくわかりにくいという特徴があるそうです。グラフで示された「累積大腸がん発生率」は、10年で2.1%、20年で8.5%、30年で17.8%となっていました。そのため、発症から8年以上の長期経過例で、特に「左側大腸炎型」「全大腸炎型」の患者さんは、定期的な内視鏡検査(サーベイランス内視鏡)が強く推奨されるとのことです。
内科治療の効果が十分に得られず日常生活が困難な、いわゆる「難治例」は、相対的手術適応となるそうです。頻繁に再燃を繰り返すような場合や、寛解導入療法を行っても炎症が治まらない慢性持続型なども、この難治例に含まれます。また、「内科的治療で重大な副作用が発現する可能性が高いケース」も、手術適応となることがあるそうです。具体的には「ステロイド長期使用による骨粗しょう症や大腿骨頭壊死」「抗TNFα抗体やタクロリムスによる感染症や腎障害」など。また高橋先生は、「腸管外合併症の一つである壊疽性膿皮症などは大腸の切除で症状が改善することが多いので、相対的手術適応となる」と、手術によるメリットについても述べました。
潰瘍性大腸炎の術式、それぞれの特徴は?
潰瘍性大腸炎における手術は原則、「大腸全摘術」です。術式は一般的に、根治性と自然肛門温存の両立を目指した「IAA(大腸を全摘し、回腸嚢を肛門につなぐ術式)」と「IACA(大腸を全摘し、1~2cmの肛門管粘膜を残して、歯状線の口側で回腸嚢を肛門管につなぐ術式)」のいずれかが行われます。高橋先生は両術式の違いについて「IAAは手縫いで、直腸粘膜はほとんど残らず、肛門括約筋への影響はややある。IACAは自動吻合器を使用する、直腸粘膜は少し残り、肛門括約筋への影響は少ない。当院では、IAAを2期か3期分割で行っている」と、述べました。
また、患者さんからよく寄せられる質問として「大腸を全摘しても水分の吸収は大丈夫なのか?」という疑問を紹介し、「水分と電解質は、実は小腸で吸収される方が多いので、大きな問題はない」との見解を示しました。
軽微な病変は残しても再発率は変わらないため、小腸の切除は最小限に
クローン病の緊急手術適応で最も多いのは「狭窄」で、「瘻孔」も自然には塞がらないので、手術になります。
その際の注意事項として高橋先生は、栄養の吸収が不十分となる短腸症候群になるのを避けるため、小腸の切除はできるだけ最小限にする必要があることを挙げました。短腸症候群は残存小腸が100~120㎝以下で発症するとされています。高橋先生によると、「狭窄や瘻孔を伴わない軽微な病変は切除せずに残す場合もあるが、病変の範囲を全て切除しても、軽微な病変を残しても、再発率は変わらない」そうです。同じく、瘻孔を伴わない短い狭窄部に対しては、「狭窄形成術」という病変を残す手術を行っているそうですが、再発率に差はないとしています。
クローン病の手術後再手術率、肛門病変合併率は?
クローン病は腸管の全領域に生じ得る再発性の病気であるため、10年間で3~7割くらいの人が再手術になるのだそうです。クローン病術後の再発予防のための治療手段として5-ASA製剤、免疫調節薬、抗菌薬、生物学的製剤、経腸成分栄養などが使用されていますが、特にインパクトの大きいものとして、高橋先生は生物学的製剤を挙げ、以下のようにコメントしました。
「クローン病の初回手術後5年以内に再手術になる患者さんの割合は、2002年以前は32.9%だったが、2003年以降は6.3%と減っており、2002年に最初の生物学的製剤が登場したことが関係していると考えられる。術後再発予防に大変有効な生物学的製剤ではあるが、一方で副作用もあるので、術後症例の全例に生物学的製剤を使うのではなく、再発予防戦略の最適化が必要だ。具体的には、手術後はまず生物学的製剤以外の維持治療を行い、半年後に内視鏡検査を行い、再発がない患者さんに対しては今の治療を継続し、内視鏡的再発が認められた患者さんに対しては生物学的製剤の導入など、治療の強化を検討するのが望ましいと考える」
クローン病の肛門病変に関しては、約5~8割の患者さんに合併するそうです。クローン病の痔瘻は肛門潰瘍に起因したものなので、普通の痔瘻と異なり手術で治すことが難しく、まずはシートン手術で患部にゴム紐を挿入して排膿を図り、肛門の痛みと腫れを取ります。その後、生物学的製剤などの内科的治療を行い、肛門潰瘍と痔瘻の治癒を目指します。高橋先生は「今年9月にクローン病に合併した痔瘻に対する再生医療等製品「ダルバドストロセル」が製造販売承認された。どのような痔瘻が良い適応となるのか今後の治療成績に期待したい」と述べました。
「外科医の痛みが、患者の痛みを和らげる」という熱い思い
最後に、高橋先生はIBDの外科治療について「IBDでは、傷が小さく早期の社会復帰が可能など、メリットの多い腹腔鏡手術が積極的に行われるようになってきた一方で、症例によっては手術難度が高く手術時間が延長しやすいというデメリットもある。最近では、特殊なメガネを装着して行う3Dの腹腔鏡手術も普及が進み、手術難度の低下と安全性向上につながっている。また、より繊細な手術操作が可能とされるロボット手術もある。ロボット手術については、現在はまだ悪性腫瘍のみの適応となっているが、今後の適応拡大に期待したい」と締めくくりました。
講演中、高橋先生がおっしゃっていた「外科医の痛みが、患者の痛みを和らげる」という言葉がとても印象的でした。これは、「外科医は難易度の高い技術だとしても、患者さんの痛みを和らげるために、努力して技術を身につけなければならない」という意味です。普段なかなか知ることのできない外科の先生の熱い思いを、この言葉を借りて、みなさんにお伝えできればと思います。
(IBDプラス編集部)