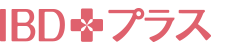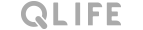腸内細菌が作る低酸素環境で、独特な「腸炎抑制細胞」が増えるメカニズムを解明
腸炎を抑制する独特な細胞「DPIEL」、酸素の少ない環境で増える仕組みは謎だった
慶應義塾大学医学部内科学教室(消化器)の原田洋輔特任助教、内視鏡センターの筋野智久専任講師、内科学教室(消化器)の金井隆典教授らの研究グループは、小腸の上皮直下に存在する腸炎抑制細胞が、腸内細菌によって形成される「低酸素環境」に適応し、増加する仕組みを解明したと発表しました。
私たち哺乳類の腸は、常に食物や病原菌などの異物にさらされています。腸組織は外界との境界にあたる組織で、栄養など「物質の取り込み」と「バリア機能」を担う腸上皮細胞が層になり、境界線を形成しています。
この境界線にはさまざまな免疫細胞が存在します。特に、小腸上皮間に多く存在する「CD4+CD8αα+細胞(DPIEL)」は、腸の炎症を抑制する役割を持つことが知られています。しかし、発生と維持などに必要な因子は明らかにされていませんでした。特に、哺乳類の細胞が生存するには「酸素」が必要ですが、腸管内の低酸素状態でどのように細胞が発生維持しているのかは不明でした。
酸素量に関わる遺伝子の調節で特定の免疫細胞を制御する新しい治療法の開発に期待
そこで研究グループは、「腸内細菌が存在する環境」と「無菌環境」で飼育したマウスの小腸で、組織の酸素濃度を比較しました。その結果、「腸内細菌が存在することで小腸の上皮層が低酸素状態になる」ことを発見。さらに、「低酸素状態ではDPIELが増加する」ことを発見しました。
これらのことから、DPIELが「腸内細菌が作る低酸素状態に適応」する細胞集団であることが明らかになりました。さらに、DPIELの発生・維持に必要な遺伝子群を突き止めることにも成功しました。
さらに詳しい研究により、DPIELになる細胞は、腸管上皮にやってくる前に低酸素に適応するための複数の遺伝子を高発現させ、その後、腸内細菌によって形成された低酸素環境にやってきて、高発現していた遺伝子を調節して発現を抑えることで、酸素需要が少なく炎症の抑制にも働くDPIELになることがわかりました。
「さらなる研究の進展により、酸素化や低酸素における発現遺伝子を中心とした新しい治療開発につながることが期待される」と、研究グループは述べています。
(IBDプラス編集部)